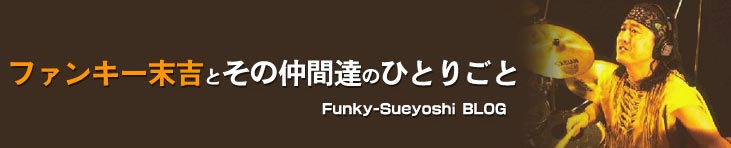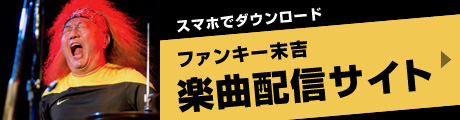2012/09/07
バラードにおけるドラムの叩き方
中国のTwitter「微博(WeiBo)」でやたらRTが回って来るので見てみたら、
この曲が回って来てた。
想你

艺人:老五
作词: 老五
作曲: 蒙古民歌
编曲: 关天天
吉他: 高飞
贝斯: 仮谷克之(日本)
鼓手: funky末吉觉(日本)
おうっ!!これは!!!あの時レコーディングした曲ではないか!!!
ちょうどバラードにおけるドラムの叩き方をブログに書こうかなと思ってたので、
この曲を使って説明したいと思う。
こちらで音楽を聞くことが出来ますのでどうぞ。
(中国バランスでドラムが小さいのが残念ですが・・・)
まずバラードなのだから「優しく」叩く部分がほとんどなのだが、
そこでまず根本としてわかってなければならないことがある。
それは
「スローボールは決して力のないボールではない」
という原則である。
「巨人の星」という昔の漫画で、
主人公の星飛雄馬は、最後に大リーグボール3号という魔球を編み出す。
力一杯投げるその超スローボールは、
その反動が自身の筋に大きな負担をかけ、
そして自らその野球生命を断った。
バラードのドラムもこのように「命をかけて」小さな音で叩かねばならない。
中国でも若いドラマーがバラードを叩いているのを見て思うのだが、
ただ「弱く叩いている」のでは何の意味もないのだ。
ニュアンスを言葉で言うのは難しいが、
「大きな爆発力を秘めて小さな音で叩く」とでも言うべきか・・・
ワシは山ほど中国のレコーディングの仕事をしたが、
そのほとんどはバラードである。
自分のドラムを聞くと、
「ああ何て悲しいドラムを叩くのだろう」
と思うことがある。
それなりに歳を取って世の中のいろんな悲しみも分かって来て・・・
というのもあるだろうが、
実はこれにはひとつのテクニックがあるのだ。
例えばこの曲の場合、
1分25秒辺りからサビが始まるが、
ドラムは決して100%爆発してはいない。
サビは短く1分38秒辺りでいきなり終わるのだが、
ワシはその瞬間が一番「悲しく」感じる。
このドラムは実はとてつもない爆発力を秘めているのに、
それを押さえて押さえて一度ドバラドンと締める。
そこにワシなんか
「人生にはどうしようもないこともあるんだ」
と聞こえてしまって仕方がないのだ。
音の大きなドラマーが、精一杯音を押さえて叩いている音色と、
音の小さなドラマーが精一杯大きな音を出している音色とは、
例えそれが同じ音量の音であろうが根本的に違うものなのだ。
だからドラムは音の大きな方が「表現力」が大きいということになる。
出力の大きなスピーカーの方が音がいいのと同じ道理である。
とてつもなく大きな爆発力を、
とてつもなく大きな力で押さえて叩いている・・・
それが「悲しさ」として伝わって来る。
この曲はどんどんと盛り上がってゆくのだが、
90何パーセント爆発するものの、
最後までドラムは「押さえている」のだ。
それが「悲しさ」となって聞こえて来るのである。
それはその後ろにとてつもない爆発力が聞こえて来て初めて感じる感情なのである。
そして音粒の揃え方・・・
私は基本的に大きく分けてスネアを4種類の叩き方で叩く。
一番フォルテシモは全力でリムショットを叩く。
(リムとヘッドを同時に叩くの意味)
毎回同じ角度で叩けるように、
左手を振り下ろして膝に当てた時にちょうどリムショットになるようにスネアの高さを調整してある。
(だからワシの左ひざは、左手が当たる部分はもう痣になっている)
そしてピアノシモの音では、左足をちょいと爪先立たせると、
リムショットにはならずAメロなどに使う優しい音色にすることが出来る。
大事なことはその叩く強さが常に均一であることである。
この曲のAメロの時に、一瞬ボーカルは強く歌うが、
ドラムはそれについてゆかずに淡々と叩いているところが「悲しい」。
(2拍目はリムのみ、4拍目はスネアでその音色を参照のほど。リムのみの音がスネアより大きいのがちと残念だが・・・)
まあ特にこのスネアのショット、
この時に毎回強さや音色が変わったりしたら興ざめなのである。
このふたつの音色の間に、
「リムショットはするが弱く叩く音色」
と
「リムショットをしないが強く叩く音色」
も合わせて4種類を使い分ける時があるが、
どの道いちばん大切なのは、
その音色を「全発同じ強さで同じ音色で」叩くことである。
あとはリズム感と言うかグルーブ感。
8ビートを遅くしたのがバラードのリズムであるが、
実は頭の中では8分音符ではなく16分音符、
特にこのぐらいのテンポの曲だと頭の中では32分音符が鳴っている。
2分30秒辺りのサビの繰り返しのフィルなどは、
音符としてはタコトコタコトコの16分だが、
ノリとしてはタットコトットコタットコトットコと倍のビートが聞こえて来る。
このビートが頭の中で鳴っているか鳴ってないかが大きな違いである。
2分50秒辺りからの間奏は、
音符は16分だがノリは32分である。
フィルも段々32分音符が増えて来て盛り上げるが、
32分を叩いてない時にもそのビート感があるかないかで「リズム」というのは大きく違うのである。
3分15秒辺りに非常にシンプルなフロアとスネアの8分打ちがあるが、
これを8分のリズム感で取ったのでは全然間持ちがしない。
ドンドンドンドンと聞こえるこの音の裏で、
聞こえてないドコココドコココドコココドコココのこの細かいリズムが鳴っていて初めてこのフレーズは成り立つ。
まあフィルだけではない。
全体的にその細かいビートがあって初めてリズムが成り立っているのである。
少々余談にはなるが、
リズム部分でも実は「ゴーストノート」というのを多用している。
ドラムをソロにして耳を凝らして聞かなければ聞こえないが、
8分音符しか聞こえてない部分にも実は、
聞こえるか聞こえないかの音量で16分音符の小さなスネアの音が入っているのだ。
このボリュームコントロールは実は非常に難しい!!
フォルテシモの音が毎回同じ音量で同じ音質である訓練はされているが、
このように聞こえるか聞こえないかの音量の音を全く同じにコントロールするのは至難の技なのだ。
ゴーストノートを入れたはいいが、
音量や音質がまばらで、時々聞こえたりなんかするとビートが無茶苦茶になってしまう。
いろんなゴーストノートがあるが、
1小節のパターンだとすると例えば、
ひとつ目はベロシティー10、ふたつ目は30、
小節の最後はちょっと聞こえるように50とか、
それは決めてしまえば次の小節も全く同じく叩く。
レコーディングの時にワシは、
1小節目を何度もやり直して、
うまく抜けたらそのまま全部ぶっ続けで録音したりするのは、
要はこの組み合わせを作っているのだ。
人間だからそんなに機械のように正確には同じにならない。
しかしそれを「命をかけて」同じにするところに「戦い」がある。
例えば2番になってベロシティー10のところを20で叩いてしまった。
そしたら2小節目から命をかけて同じく20で叩くのだ。
その「戦い」の連続を「リズム」と言う。
「フィルを叩いたらちょっとだけ速くなった!!」
アドレナリンが出まくっている頭の中では、
それはスローモーションのように次の1発で何とかしようとする。
「あ、この1発がほんの少し大きかった!!」
次の1発で何とか解決しようとする。
その連続を「リズム」と言う。
ワシはこれを「初恋」に例えて説明したりする。
強く抱きしめたら壊れてしまう。
弱く抱きしめたら逃げてしまう。
だから命がで一番相応しい力で叩き続ける。
何故命をかけられるのか、
それはひとえに「愛」である。
その「音楽」を壊したくないという「愛情」
「絶対に壊してはいけない」という「責任感」
つまり「リズム」とはそれを叩く人の「人生」なのである。
そして最後に、
「ドラマーはバンドの指揮者である」
1曲をどのように盛り上げて、
ある時は強く歌い、ある時は弱く歌い、
それは歌手がやっているのであるけれど、
作り上げているのは実はドラマーなのである。
アレンジャーが作り上げたこのややこしいセクションを、
ワシは「自分の歌い方」で歌い上げる。
その中には「こう歌ってくれ」というのが強くある。
朋友がこの曲を引っさげて、
零点(ゼロポイント)のみんなを蹴散らして世に出てゆく。
その姿を想像しながら構築した。
願わくば実世界でもそのようになって欲しいと心から願う。
頑張れ!!朋友よ!!
羊肉の恩がある!!ワシはお前のためなら何でもやるぞ!!(笑)