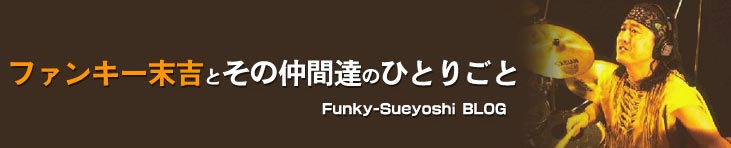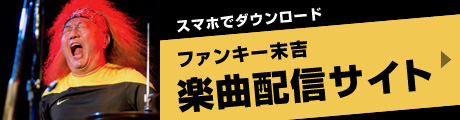2012/09/09
ドラムのチューニングの仕方
三田悟志というブルースギタリストとツアーを廻っている。
毎日違う土地に行ってドラム叩いて酒を飲む生活は理想なのであるが、
ひとつだけ、まあちょっとだけめんどくさいのが毎回のドラムチューニング・・・
ピアノはどんな小屋でも必ず調律師がチューニングしてくれているが、
ドラムという楽器はどうしてもそこまではいかない。
ドラマーは調律師も兼ねているというのが現状である。
まあ「大事な話」と「大雑把な話」と混ぜこぜにして書いてゆくが、
まずは「大雑把な話」・・・
Pearlドラムのモニターをさせてもらってもう30年近くになるが、
ある時、パールのモニター担当の人からこんなことを言われたことがある。
「ファンキーさん、長年モニターやって頂いて本当に感謝しているのですが、
言っちゃぁナンですが、ファンキーさん、どのドラム叩いても音いっしょ!!(笑)」
まあドラマーとしては最大の「褒め言葉」なのだが、
モニターとしては・・・(苦笑)
まあ叩き方のタイプとして、
「力でねじ伏せてドラムに最大の音量を鳴らさせる」
まあつまり「悲鳴」みたいなもんなので、
スネアのチューニングなどはまあどうでもいい。
(これかなり「大雑把な話」)
とりあえず上下の皮ともギンギンに強く張って、
リムショットで思いっきりカンカンぶっ叩けば、
隣の和佐田が顔をしかめるような音は鳴る!!
(よいこは決して真似しないよーに!!)
バスドラっつのはもともとその独特な奏法により、
踏んでそのままペダルが皮に当たったまま止まっている、
つまり叩いてすぐにミュートしているわけだからチューニングなどどうでもいい。
(これもかなり「大雑把な話」)
問題はタムである!!(これホント)
ドラムセットのいわゆる「太鼓」の中で、
その音の残響音が一番長いのがタムなのである。
(ここから段々「大事な話」に移ります)
さて、ライブハウスに行くと、
たまにタムのヘッドにビシバシガムテープを貼っていることがあるが、
タムの残響を抑えようという目的ならこれは実は間違いである。
だいたい、ギターやベースが鳴り過ぎるからと言ってボディーや弦にガムテープ貼りますか?!!(笑)
実験してみればわかるが、
ガムテープを貼ったところで残響の時間はそんなに変わらない。
変わるのは「倍音」、
つまりアンバサダーなどの薄い皮を打面に貼っている時、
倍音が多すぎてカラカラ言う時には効果的であるが、
残響を短くするならそれはチューニングのバランスを崩すしかない。
つまりそうなるとどのみち「鳴らなく」なる。
ドラムなんて鳴ってなんぼのもん!!
いい音よりも何よりも「大きな音」で鳴ってればそれでよい!!
(これ「大雑把」だけどかなり「ホント」)
昔はレコーディングでもライブでも、
新人バンドはエンジニアより立場が弱いので、
「タムがワンワン鳴ってて音にならないよ」
と言われて泣く泣くガムテープ貼ったりいろいろしてたが、
ワシは最初にアメリカでWyn Davisとレコーディングしてその考えは間違いだと悟った。
彼はワシに言った。
「タムの表の皮と裏の皮を同じチューニングにしろ」
と・・・
通常、表の皮を裏の皮より緩くすると叩いた瞬間より音が低く下がるベンドダウンする音になり、
同じチューニングにすると共鳴していつまでも同じ音が長く鳴るようになると言われている。
つまり日本のエンジニアが言ってたこととまるで逆のことを言ってるのである。
ちなみに裏の皮を表の皮より緩くするとベンドアップする音になる、
と昔ドラムマガジンに書いてあるのを見たがこれはウソである。
やってみればいい。音が鳴らない(笑)
さてWyn Davisの話に戻るが、
結局はワシのチューニングでは満足せず、
結局プロのチューナーを呼んだわけだが、
その音が非常に素晴らしく、
以来、ワシはそれが頭に残っているのでそれになるだけ近づけるようにチューニングしている。
ボーイソプラノにテノールのパートを歌わせたり、
テノール歌手にソプラノを歌わせても無理なのと同じように、
それぞれのタムにはそれぞれ一番よく鳴る音程があり、
それはだいたいチューニングキーを締める時の手加減でわかる。
そして実は間違った考え方をしてる人が多いのだが、
ひとつのタムを叩いた時に、隣のタムが共鳴するのは実は「当たり前」なのである。
共鳴しないようにガムテープをビシバシ貼るのではなく、
めいっぱい共鳴させて、それが不協和音にならないようにそれぞれの音程を調整するのだ。
つまり「ドン」と叩けば「ワン」と鳴る。
それがタム!!要はその「ワン」全体が気持ちよければそれでいいのだ。
つまり「ド」の音のタムを叩いたら隣の「ソ」の音も鳴る。
それが「ソ#」だとちとキモチワルイ・・・という感じである。
「ドミソ」とかになってしまうと「調性」が生まれて曲のキーと違うとキモチワルイので音程差は4度がよいと言われたりしているが、
もともとティンパニではないのでタムの音程をそんなに厳密に固定するのも難しい。
また裏表の皮は違うもの(通常打面は厚い皮で裏は薄い皮)なので、
上下の皮を全く同じ音程にするのもなかなか難しい。
要はタムが一番よく鳴ってて、
それが変に干渉してワワワンという変な倍音が鳴らなければそれでよい。
完璧主義でタムのチューニングなんてしてたら何時間かけても終わらないので、
それこそここはある程度大雑把にやらねばならない。
(これ悲しいけどホント)
そこでワシはいつも思うのだが、
よくある4点セットのドラムセットのタムの口径はどうして12、13、16なのだろう・・・
スネアが14インチなので14タムと共鳴しないようにと言うが、
もともとスネアは12インチのタムより高い音にチューニングするので共鳴しようがないのだ。
12インチが一番よく鳴る音程と13インチが一番よく鳴る音程差は近く、
全体がよく鳴る音程差にするためにはどちらかを少し犠牲にせねばならない。
だからワシは自分のセットは8、10、12、14、16と全部偶数で揃えている。
まあしゃーない!!それがイヤだったら自分のセットを持ち込むしかないのだ・・・
今日の小屋のドラムはどんなかな・・・
それも含めて、その日のチューニングも含めて、
そして叩き手の体調や精神状態、
そしてバンドのコンビネーションも全て含めてその日の「音」が決まる。
だから「ライブは水モノ」、面白いのである。