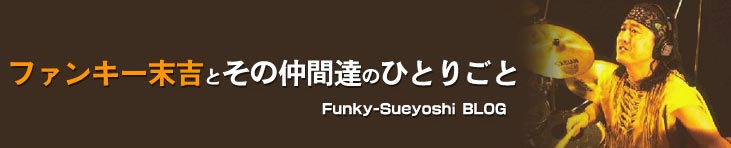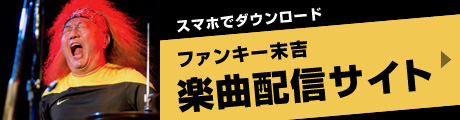2009/03/30
ラテンのドラム、Jazzのドラムとは・・・
3月28日SOMEDAYのラテンJazzのビッグバンドに呼ばれて叩いてきた。
前回の時はパーカッションの伊達弦以外は全員初対面だったのでかなり面喰ったが、
今回は半数が顔見知りなので気が楽である。
このバンドは鬼瓦みたいな顔したSOMEDAYのマスターがバンマスで、
何故か毎回毎回メンバーが変わるので大変である。
もともと、「末吉くん、やってみるか?」で始まったのであるが、
人のプレイにいろいろケチをつける厳しいバンマスなのが何より大変。
でももともと私はこうしてJazzドラマーとして育ててもらったんだから、
これが実は何よりありがたいことなのである。
前回は「バスドラとパーカッションがぶつかる」と文句を言われ、
挙句の果てには「バスドラを踏むな」と指示が来る。
まあJazzの人もラテンの人もバスドラはオカズに入れるぐらいで、
基本的にはリズムパターンに必ず入れるものでもない。
ジャンルが変われば叩き方は180度変わるのである。
ラテンもオルケスタ・デラルスの連中とのセッションでいろいろ勉強させてもらったので、
今回は北京からティンバレスを持って帰って来た。
嫁の荷物なんかも頼まれて持って帰ったので超過料金2万円・・・・。
勉強代もいろいろかかって大変である。
ローディーの関山くんと早めにSOMEDAYに入って、
あーでもないこーでもないといろいろセッティング。
前回の感じでは必ずしもラテンの曲ばかりではないし、
必ずしもJazzの曲ばかりでもない。
ソロになればタムも叩かねばならんし、
ティンパレスを中心にラテンセットを組むはずだったのが、
こんなに大所帯のマルチセットになってしまった。
叩いてみてこれが非常にフィットして気持ちよかった。
ラテンの曲は身体をちょっと右向きにしてカウベルを中心に叩き、
Swingの曲は正面に向けてSOMEDAYのJazzセットを中心に叩き、
ソロになるとちょっと左に向けてロートタムを中心に叩く。
ただラテンのティンバレス奏者のように、
ラテンになるとバスドラを抜いて
完全に手だけで叩いてリズムを叩こうと思ったが無理だった。
1小節ぐらいでもたなくなってしまいつい足を入れてしまう。
ワシはパーカッション奏者なのではなくドラマーなのだと実感。
おかげでリズムパターンが変わる瞬間の数小節はリズムが定まらない状態が続いたが、
マスターの評判は上々だった。
「末吉くん、なかなかよかったで。
普通ロックの人がJazz叩いたらな、レガートだけで全部ぶち壊しや。
でもな、今日はある程度形になってたで。
ある種の匂いがある。
末吉くん、Jazz好きやろ。
この匂いが出せたら基本的にはOKや。
頑張りや!」
鬼瓦のようなマスターに褒められたのは久しぶりである。
残念ながら5月のこのセッションはXYZとぶつかって参加出来ないが、
次のセッションではまた精進したいと思う。