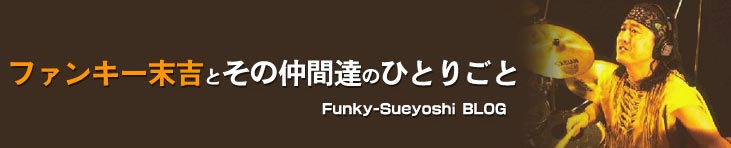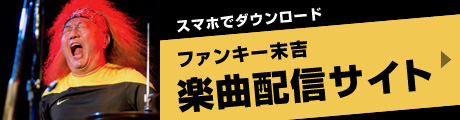2018/09/16
布衣秋のツアー2018山西省「太原」
太原は一昨年の中国でのドラムスクールの場所である。
この時は北京から飛んだんだけれども、
布衣のツアーはうまいこと組んでいて、河北省「邢台(XingTai)」から高速鉄道で3時間足らず・・・まあ東京から大阪まで行くみたいなもん・・・
・・・などと考えていたが、もう寄る年波のせいか2時間以上って結構こたえるのよねぇ・・・(>_<)
でもこの日は移動日なので大丈夫!!
末吉の強い要望により(笑)みんなで焼肉!!
食って飲んでゆっくり寝て、鋭気を養って次の日本番!!
・・・しかし毎度の通りスタッフと共に会場に一番乗りして唖然とするのである・・・
なんと会場がまだ出来ていない!!!(◎_◎;)
いや〜中国で活動し始めてもうすぐ30年、さすがに着いたら会場がまだ出来てなかったのは初めてやな・・・(笑)
まあ会場というか、会場が入っているショッピングモール自体が翌日オープンなのに全く出来上がっていない!(◎_◎;)
建物全部がまだ工事現場という状況で、
明日のオープンのためにせっせとコップを拭いているお姉さんたち・・・
今拭いても無駄やと思うで・・・(笑)
お嬢さんたちこのホコリだらけの中で食器拭いても無駄やと思うで〜(笑) pic.twitter.com/cirEB9aofX
— FunkySueyoshi (@FunkySueyoshi) 2018年9月14日
さてそんな工事現場に機材運んでセッティング〜
でもここでまた大問題が・・・
ギターアンプに電源ノイズが乗る(>_<)
まあハコ自体がまだ出来上がってないんやから電源までは無理やろな・・・(笑)
立ち位置変えたり、無音状態では音を絞るとか、なんとか騙し騙しリハーサルは終了!!
ところがこの時にあまりのトラブルのために見落としていたのだ・・・
このドラムは鳴らない・・・(>_<)
最初は、狭いステージだし、音が回ってるからドラムの音が抜けて来ないのかと思っていた。
客が入れば低音が吸われてちゃんと抜けて来るだろうとタカをくくっていたのだ・・・
まあサウンドチェックの時にあんまし鳴らないことはわかっていたが、
これぐらいなら本番の「叩き方」で何とかなるだろうとタカをくくってたら、
本番になってみたら全くそのレベルではなかったのである・・・(>_<)
さて、ここからはカテゴリー「ドラムの叩き方」の分野であるが、
ではその「叩き方」ってどうするの?・・・という話である。
まず私は、中国ではよくびっくりされるが、自分のドラムの音はモニターで返さない!!
「え?!どうしてですか?!よく叩けますねぇ・・・」
とよく言われるが、
そんな時にはマイケルジャクソンが映画の中でイヤモニを拒否するようにカッコつけてこのように言うことにしている・・・
「俺の時代にはモニターなんかなかったからよう・・・」
大概の中国人はこれでノックアウトされて、ヒドい時には私を拝み始める(笑)
いや、厳密に言うとアマチュアバンドの頃にはモニターなんかなかったが、
爆風スランプの頃にはもちろんちゃんとあった。
でもやっぱアマチュアの頃の名残りであまり自分の音は返してなかったように思う・・・
一度、ツアーの移動日に博多でハウンドドッグのコンサートをリハから見せてもらったことがあるが、その時にドラムのブッチャーさんが自慢のモニターシステムを披露してくれた。
ドラムの左右にどデカいスピーカーを置いて、
「俺はなぁ、外のPAの音がそのまま聞こえてないとイヤやねん」
と言ってドラムを叩いてくれたが、それはそれは「完璧な音」である。
いや、それはそれで「完璧」なのだが、
私は自分でそれを真似ようとは思わなかった。
PAの音は所詮「PAの音」であって、
ドラムの音は、生音をこの耳の位置で聞いているのが「ドラムの音」である。
亡くなったひぐっつぁんも、
「俺はなぁ、自分のドラムセットとこのモニターシステムが用意出来んライブは基本的にやらへんから」
と言っていたが、
「毎日ドラムを叩いて生活したい」という夢から今に至っている私としては、Jazzクラブから武道館コンサートまで全く同じシステムというわけにはいかんし・・・
中国のミュージシャンは、ライブハウスに立った時からモニターがあったし、
ドラマー以外にもギターやベースなども必ず自分の音が返っているのが当たり前だった。
私の時代にはこのぐらいの小さいステージではアンプの生音を聞いてたし、
モニターに頼るなら「足りない音をちょっとだけ返す」程度である。
ところが今回のこのステージ、
ステージ上で音が回ってドラムの音が聞こえない・・・
というよりドラムが全く鳴ってくれない(>_<)
いつもモニターなんかもらってないので、
うちのエンジニアなんか、もうドラムのところにモニタースピーカーすらセッティングしていない(笑)
でももしモニターがあって、自分のドラムの音を返してもらったとしたら解決するのか?
・・・いや、それは否である。
音量の問題ではない「音質」の問題なのだ。
「鳴ってない音色」はどれだけマイクで増幅したって「鳴ってない音色」でしかない。
音量という点では、人間の耳は、ある音に集中するとその音だけを増幅出来るという能力がある。
こればかりはAIがどれだけ賢くなっても人間にしか出来ない芸当である。
だから自分の生音を一生懸命聞く!!
いつものように「パーン」と爆発的な音色にならないのならスネアに当たるスティックの角度を調整する。
「ロック」の場合、基本的に全てのショットをリムに当てる。
リムとヘッドとを両方同時に当てるのである。
レギュラーグリップにドラマーは時々スカっとリムだけになって不発に終わるショットもあったりするが、
私の場合はスネアの高さを、ちょうど左手を左足のつけ根に置いた時にリムショットとなるように調整している。
だから左足の付け根にはアザが出来ていて、そこだけ毛が抜けている(笑)
左足を爪先立ちにするとスティックの角度が上がり、下げると深いリムショットになる。
これでAメロやサビなど、音色を使い分けているのだ。
まあ乱暴に言うと、リムショットを深くするほど甲高い音になり、
浅くするほど優しい音になる。
バラードなどでは
「スローボールは力のないボールではない!!力いっぱいゆっくりのボールを投げるのだ」
の原則の通り、弱く叩くだけではダメである。
この「優しさ」と「爆発力」との割合を、このヒザの角度が決めてくれるわけですな。
こんなことを言うと、「コントロール能力」というか、「物理的な運動能力」でそれをコントロールしているように思われがちだが、それは違う。
大事なのは筋力とか運動能力ではなく「耳」なのである。
ステージ上のそんな真っ白になった頭でモノを考えることなど出来やしない。
「耳」で聞いて、「耳」が「気持ちいい」と感じたら「耳」が「そのままキープしろ」と命令を出す・・・そんな感じである。
だから必然的にモニターから返って来る「作られた音」ではこの辺の微調整がやりにくいのである。
さて、このドラムセット・・・鳴らない・・・
通常の場合、どうするかと言うと、まずスネアのピッチを上げてやる。
単純に言って甲高い音の方が周波数的に「抜けて来る」からである。
だが、このスネアはダメ(>_<)もう既にパンパンで皮自身が鳴ってない・・・
そういう時にはリムショットを深くしてやる。
その方が甲高い音が出るからである。
気が付いたら左足よりも低い所にまで手を下げて一番深いリムショットを叩いているので、MCの時に椅子をちょっと上げてその位置をデフォルトに直してやる。
しかしまあ「深ければいい」というわけではなく、
「パーン」という音をもっと深くすれば「カーン」になり、
最後には「カチッ」とリムだけになってしまう。
その角度は物理的なものではない。
これも「耳」が判断して、「カーン」の方に行き過ぎているように感じたら身体が自然に角度を固定しているのだろう。
ところがこのマックスでやっと音が抜けるような状態だと、
フラムショットとか・・・
(私はよくフィルの代わりに小節の最後のスネアをリムショットにしてメリハリをつけたりするが)
そのショットがいつものように「特別な音」にならないのだ。
普段はそれほど深くないリムショットをデフォルトにしてるので、
「強さ」+「根性」でフラムショットを叩くと、
音量と共にリムの深さが変わっているのだろう、ヒステリックな全く違う音になる。
(よく「ドタン」というフィルで顔じゅうに気合いを入れてフラムを叩くのはこの「+根性」の部分である)
ところがリムがこれ以上深く出来ないことを身体はもう感じてるので、
「音量」は変わっても「音質」は変わらない。
同様に弱く叩く部分でもリムを浅くすると音が抜けないので角度を変えられない。
つまり「表現の幅」がむっちゃ狭くなってしまうのである(汗)
「ドラマーは音の大きなモンの勝ち!!」
とよく言うが、「音が大きい」ということはそれだけ「表現力の幅がある」ということなのだから、この日は久しぶりに「音が小さなドラマー」の気持ちが少しわかった(笑)気がするライブであった・・・
まあそれでもちゃんと叩きました!!
客も入ったなぁ・・・ひとつのドア以外封鎖されている工事現場によくこれだけの人間が入ってこれた(笑)
ドラムソロ!!それなりに工夫して精一杯鳴らしてます!!
後にロードムービーがアップされました。
私たちは翌朝には内モンゴル呼和浩特へ向かうけど、
今夜はショッピングモールじゅう徹夜で工事して、
どこが出来上がってなくても何食わぬ顔で明日には大々的にオープンするんやろうなぁ・・・
中国・・・やはりおそるべし!!(笑)