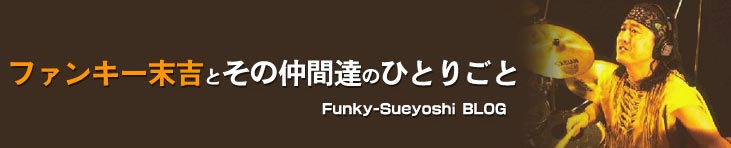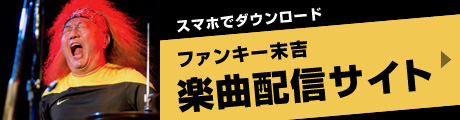2013/08/27
ドラマーとドラムセットの関係
2週間におよぶ曾我泰久のツアーを終えて香港に来ている。
嫁曰く、今月は1日しか家に帰らないそうだ(笑)
日本のライブハウスツアーでは基本的にそのライブハウスのドラムセットをお借りするのだが、
時々ぐちゃぐちゃのチューニングのドラムセットに出会うことがある。
特に前回行ったことがある小屋で、
そんなに期間が空いているわけではないのにワシが一生懸命チューニングしたドラムセットがこんなになってると首をかしげてしまう。
日本全国のライブハウスに出演しているドラマーの諸君、
もし君らの直前にファンキー末吉が出演してたとしたら、
君らはドラムのチューニングをいじるではない!!
ワシが完璧にチューニングしてるから変えるな!!(キッパリ)
まあドラムセットやヘッドの状態にもよるのだが、
毎回毎回ワシはその小屋のセットを一番「鳴る」ようにチューニングする。
前回の京都「都雅都雅」と神戸「チキンジョージ」は特にばっちしであった。
でもまあ他のドラマーに言わせれば「末吉のセットは鳴らない」という人もいる。
「力いっぱい叩いてやっとその音がする」とも・・・
ドラマーとドラムセットの関係は、
戦いに出る時に乗る馬と戦士の関係に似ている。
(以前書いた文章を読んでみて下され)
ワシの場合、スネアはリムショットで思いっきりシバいて無理矢理鳴らすし、
バスドラはそもそもが踏み込んでビーターでそのまま音を止めてしまうのでいいが、
やはり残響音が長いタムの音が一番大変である。
最近気付いたのだが、
サウンドチェックでボンボンとタムを叩いている時、
その跳ね返りなど手応えと、出て来る音のバランスで、
そのドラムセットとの付き合い方、音の鳴らし方というのが決まってゆくのだと思う。
ワシはどちらかと言うとどんなドラムセットでも力ずくで鳴らし込む方じゃが、
かと言ってドラムセットの「気持ち」も汲んであげないと鳴るものも鳴らない。
ワシがいつも使っているヘッド「クリアエンペラー」ならいつもの感じ、
「コーティッド」ならイアンペイスみたいな感じ、
と叩く側もそのドラムセットに合わせてちょっと変わってあげられればドラムセットも鳴り易いだろうと思う。
「ドラムに叩かされてる感じ」というのは、
ワシはX.Y.Z.→Aのファーストアルバムのレコーディングの時に味わった。
数々のロックの名盤を作り上げて来たこのスタジオで、
数々の名ドラマーのドラムをチューニングして来たチューナーが、
「一番ロックな音」にチューニングされたそのドラムセットを叩いた時に、
ワシはこれこそが「ロックの音」だと思った。
それがウェイン・デイヴィスが作る世界最高の音でヘッドホンから流れて来る。
あとはその「音」をこの「音符」で叩けばいいのである。
ところが叩けない。
いつもなら何でもない8ビートのリズムを1コーラス叩いただけで息が切れてしまうのだ。
ふーふーぜーぜー言いながらやっと叩き終えて思った。
もともと「ロックな音」というのはあの人たちのような、
マッチョで巨体の白人が棍棒のような手でぶん殴ってはじめて出る音なのではないか・・・
でもサウンドチェックの時にはちゃんと音が出ている。
一発ずつ叩く時には出ているんだけど、
要はそれを連続して叩けるフォームが出来てないのだと思う。
まあフォームが出来てないなら作ってやればすむことなのでよいが(笑)
ドラムという楽器は身体で叩いてはいるんだけど実際は「耳」で叩いているという部分も大きいと思う。
バンと叩いて「気持ちいい」と感じる。
その時には実際にいろんな要素が身体の動きに反映されているのだろう。
ビートを叩いているのだからそれが「連続」せねばならない。
身体というのは無意識に「耳」からのいろんな情報を処理して連続的に「動き」を微調整しているのだと思う。
「耳」からの情報というのは当然ながら「ドラムセットの音」なのだから
出る音とプレイとが密接な関係であることは自明の理であろう。
例えば樋口宗孝という偉大なドラマーがいたが、
彼のドラムセットを鳴らすのはホントにしんどかった。
(その話はこちら)
思うにひぐっつぁんってヘビーな音でスピード感を出すドラマーだったので、
彼はその重い音を力ずくで前のめりに叩いてたっつうスタイルやったんやないかな・・・
シェイカーのクドーちゃんのドラムはもっと鳴らん(>_<)
クドーちゃんの場合はどしっとヘビーにグルーブさせるスタイルなので、
そのドラムセットで手数を入れまくったりスピードドラムを叩くってしんどいのよねぇ・・・
まあそれと同じようにワシのドラムセットを人は「叩きづらい」と言うのぢゃろうが、
ライブハウスのドラムセットにあれこれ「こうであれ」などと言っても話は始まらない。
要はそのドラムセットがどんなドラムセットなのかをよく理解してやって、
それに合ったような叩き方をしてあげた方がドラムは全然よく鳴るし、
むしろそれの方が結果的に「ファンキー末吉の音」になる。
「どんなドラムセットか」というのはチューニングこそが「対話」である。
口径の小さいタムで低い音を出そうとしても無理なのと同じで、
「このドラムセットであんな音を」などと思っても「無理」である。
スネアもヘッドがアンバサダーだったりすると、
エンペラーを貼ってる時のように低めのチューニングは絶対無理なので必然的にカランカラン鳴る音になるし、
裏のヘッドが古かったりいろんな要素でスナッピーがあまり鳴らない状態のスネアもある。
でもカランカラン言ってようがドシっとしてようが、
それなりに「ファンキー末吉の音」というのは出せる。
ひぐっつぁんのドラムセットを叩いたってクドーちゃんのドラムセットを叩いたって、結果「ファンキー末吉の音」になるのである。
でもプレイの内容は少々違って来る。
重たい音のセットだと力が要るので細かいパッセージのフレーズは叩けないし、
カランカラン言うセットだと逆にスピードメタルのスタイルで叩いたりする。
実際やっちんの年頭の東京ライブでは、
そのドラムセットの音色により手数系のソロはあきらめて別のスタイルのソロを叩いている。
9月1日のファイナルでは自分のセットなのでタムも多いし手数系のソロをやるかも知れん。
(自分のドラムセットでも毎回音が違うし、自分の状態でも違ってくるので一概には言えんが)
要はその時々のドラムの鳴り方によってそれを受け止めてやれる「度量」は必要である。
自分がこんな音を求めてるからドラムセットに「そんな音で鳴れ!!」と言ってもそりゃ無理である。
ステージでの音というのはドラマーとドラムセットとのコラボレーションなのであるから、
「あんたがそうなら俺はこうするよ」
という「対話」が全面的に必要である。
Jazzのような即興性のあまりないライブでもライブが毎回違うのは、
それこそミュージシャン同士のコラボレートが違うからであり、
ひいてはそのミュージシャンのプレイが微妙に毎回違うからである。
ドラマーだけ取ってみても、
毎回同じ音符を叩いているのだけれども、そのドラムセットとのコラボレートが違うのだから、
音色をはじめ、ビートにもそれは大きく影響してくる。
それを受けて他のプレイヤーの演奏も微妙に影響を受け、
それが歌う人にも影響する。
たかだかドラムのチューニングだと思ってバカにしてると、
結果的にライブそのものを左右しかねんよ〜
繰り返し言おう!!
各ライブハウスに出演するドラマーの諸君、
ワシが数日前に叩いたドラムセットだったら悪いことは言わん、
そのまま叩きなはれ!!